💡この記事のPOINT
・スケッチ指導で押さえるべき基本ルール(大きく・簡潔に・正確に)が理解できます。
・ルーペの正しい使い方(距離の合わせ方) を授業でどう教えたかがわかります。
・授業の流れ・指導の工夫・つまずき対策 を確認でき、明日の授業にそのまま活かせます。
オリエンテーション後、初めての授業となります。
本時にてスケッチの仕方とルーペの使い方を学習後、次回校内の探索にて植物観察を行います。
4月当初は授業途中で健康診断などで中断することも考えられるため、
学習プリントは穴埋め形式とし、自主学習や宿題でも進められる形とした。
タンポポの花を持参させ、
スケッチとルーペの使い方の学習を1時間目、
生物カードを使用した校内探索を2時間目としてもよい。
| 活動内容 | 時 間 | |
| 導入 | 1.教科書を確認し、スケッチのポイントとルーペの使い方をプリントにまとめる | 10~15分 |
| 展開 | 2.タンポポの花を実際にルーペで観察しながら、プリントにスケッチを行う | 20分 |
| まとめ | 3.プリントをまとめ、グループで共有する 4.ふりかえり、次回の校内探索の予告をする | 10分 5分 |
授業の流れ|スケッチとルーペの使い方
持参したタンポポの花を丁寧に分解し、花のつくりを調べる活動を通して、ルーペの使い方やスケッチの仕方を正しく学ぶことを目的とする。
めあて|タンポポの花のつくりをスケッチしよう
準備|タンポポの花(生徒持参)、ルーペ、ピンセット、筆記用具(鉛筆必須)、プリント、セロハンテープ(プリントに貼りたい生徒用)
1.教科書を確認し、スケッチのポイントとルーペの使い方をプリントにまとめる
ルーペの使い方は、
・見たいものが動かせるときは、ルーペを目に固定し、見たいものを前後に動かす
↑今回はこちら
・見たいものが動かせないときは、ルーペを見たいものに固定し、顔を前後に動かす
スケッチをするときのポイントは、
・目的とするものを
・はっきりと
・影をつけずに
書くことです。説明も加えると◎
2.タンポポの花を実際にルーペで観察しながら、プリントにスケッチを行う
※生徒が持参したタンポポの種類の【見極めポイント】
『総苞(そうほう)』で区別する

そり返ったもの:西洋タンポポ(外来種)

そり返っていないもの:日本タンポポ(在来種)
西洋タンポポが7割、日本タンポポは3割程の持参率
3.プリントをまとめ、グループで共有する
4.ふりかえり、次回の予告をする

評価基準
1.自然現象への関心・意欲・態度
A 2種類以上のタンポポを持参することができる。または授業後、宿題として採取しプリントに添付することができる。
B 1種類のタンポポを持参することができる
2.科学的な思考
A タンポポの花について独自の視点から考察することができる
3.実験・観察の技能・表現
B タンポポの花を正しい順序で観察し、まとめることができる
B ルーペを正しく扱うことができる
4.自然現象への知識理解
授業プリント例
生徒用
教師用


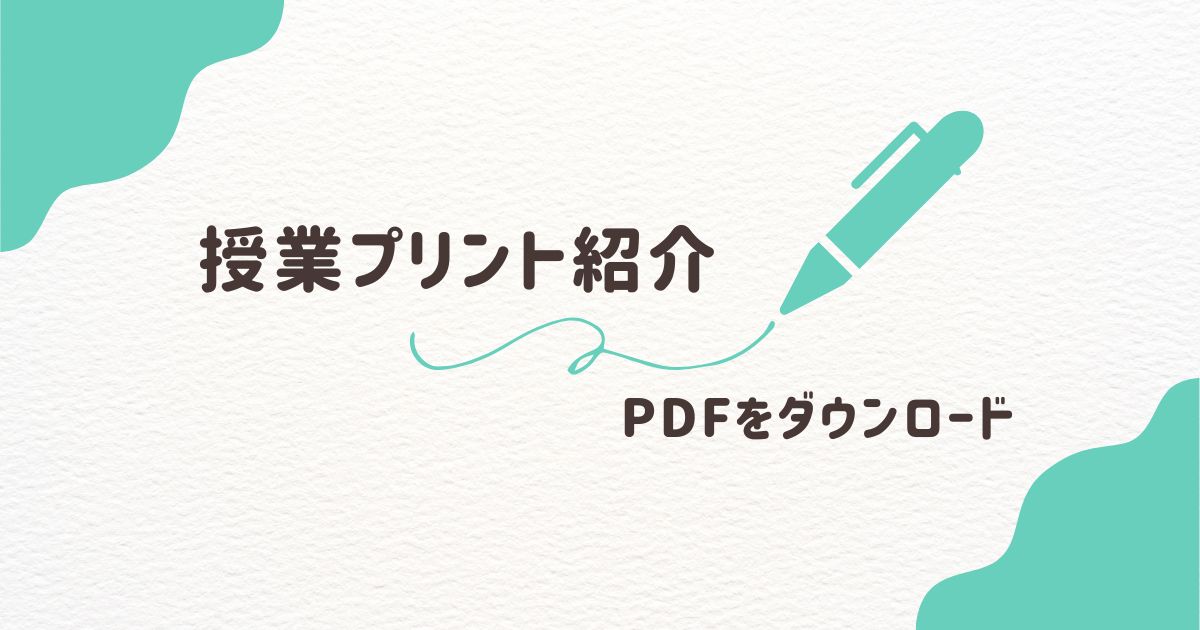
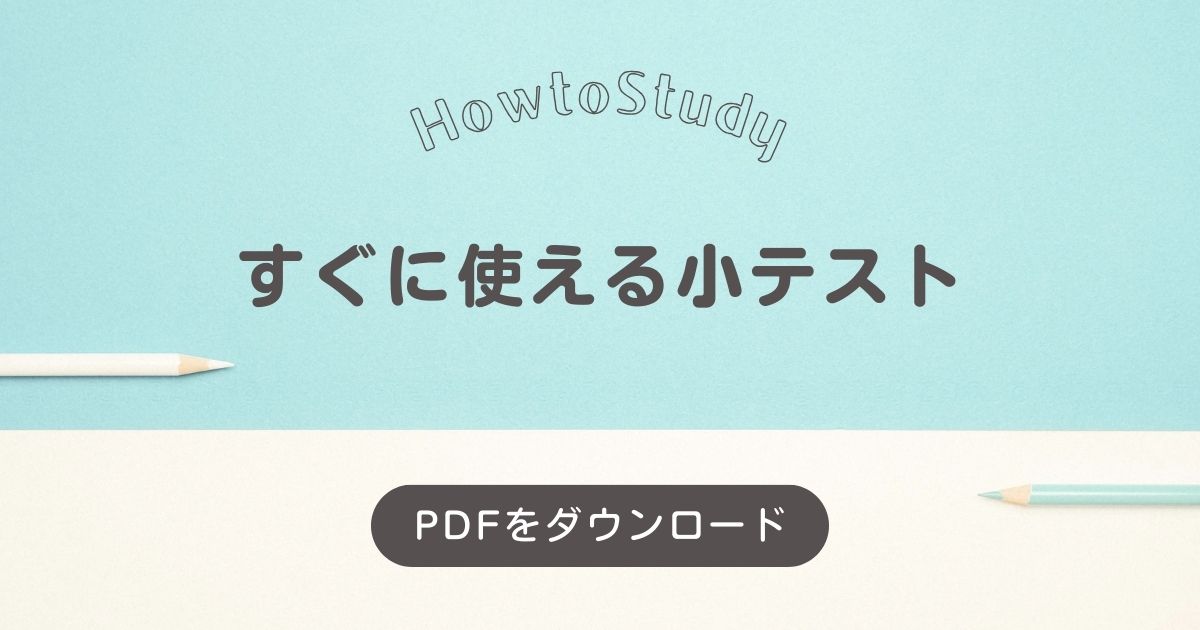
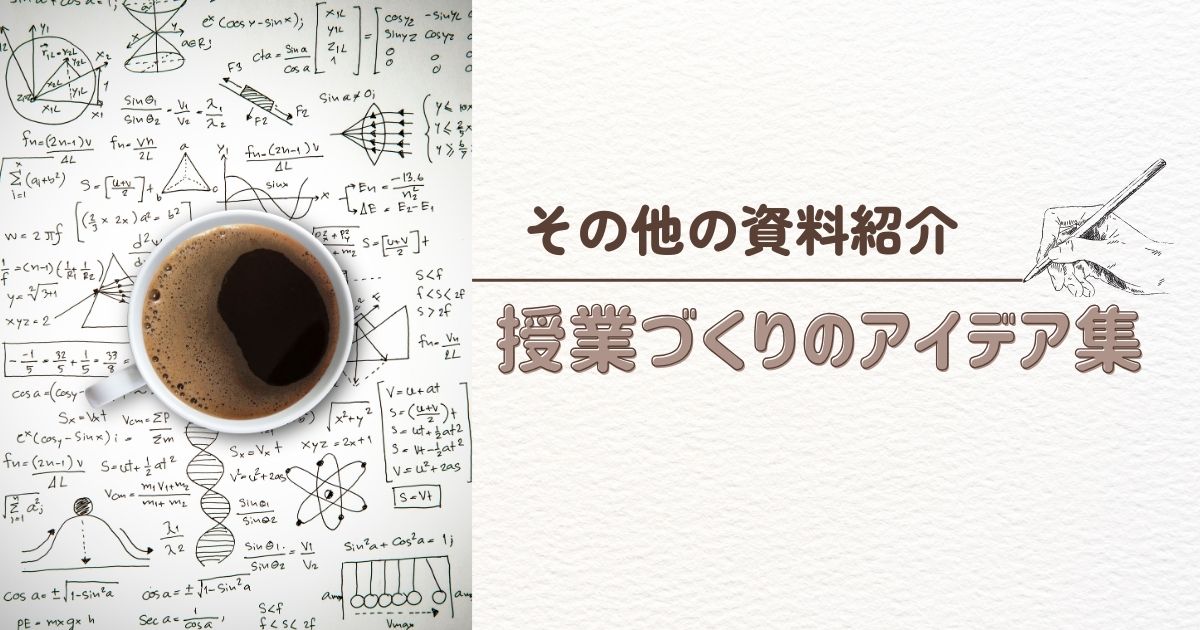
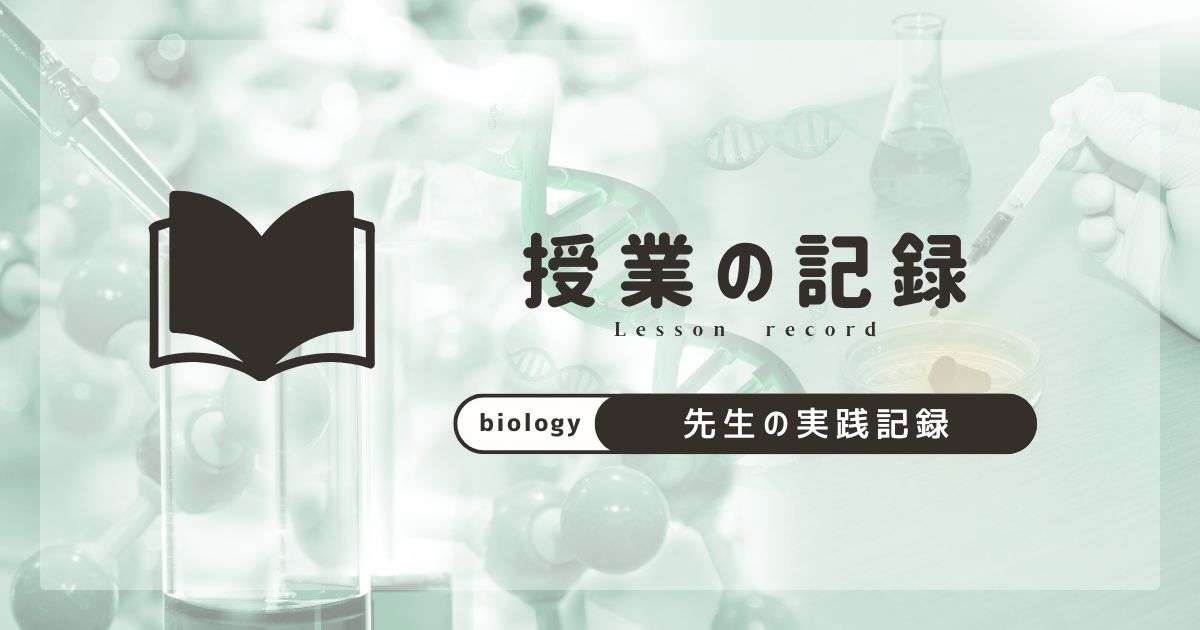

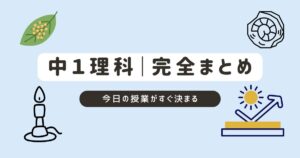
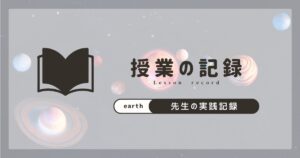
コメント