💡この記事のPOINT
・力の合成の基本概念(力の向き・大きさ・平行四辺形の法則)が整理できる
・合力を作図で求める手順 を、実際の授業例をもとに理解できる
・つまずきやすいポイントや指導のコツ を知り、授業改善に役立てられる
オリエンテーション後、3年生初めての授業になります。
本時の学習に入る前に、1年生で学習する「力の表し方」の復習を入れてもよいです。
本時では、2つの力を合成するときの表し方について学習します。
三角定規を2つ用意させると、作図がスムーズにできます。
事前の連絡を忘れずにしましょう
本時の学習の流れ|力の合成を理解する
1.2つの力と同じ働きをする1つの力を求めること→力の合成 を理解する
2.合成した力(合力)を作図によって求めることができる
めあて|合成した力を表せるようになろう
準 備|三角定規、筆記用具、学習プリント
| 活動内容 | 時 間 | |
| 導 入 | 1.教師の説明により力の合成について知る | 10分 |
| 展 開 | 2.力の合成によりできた1つの力(合力)を作図によって求める ① 2つの力が同じ方向にはたらくとき ② 2つの力が反対方向にはたらくとき ③ 2つの力が違う向きにはたらくとき | 10分 10分 10分 |
| まとめ | 3.本時の学習を振り返る | 5分 |

1.教師の説明により力の合成について知る
力の合成 :2つの力と同じはたらきをする1つの力を求めること
合 力 :合成した力のこと
2.力の合成によりできた1つの力(合力)を作図によって求める
①2つの力が同じ方向にはたらくとき
1つの物体に対して力1(F1とする)と力2(F2とする)が同じ方向にはたらくとき
合力Fは F1 と F2 の和となる
F=F1+F2
②2つの力が反対方向にはたらくとき
1つの物体に対して力1(F1とする)と力2(F2とする)が反対方向にはたらくとき
合力Fは F1 と F2 の差となる
(F1>F2の場合) F=F1ーF2
③2つの力が違う向きにはたらくとき
1つの物体に対して力1(F1とする)と力2(F2とする)が同じ方向にはたらくとき
合力Fは 2つの力を2辺とする 平行四辺形の対角線 となる
※2つの力の角度が大きくなると、合力は 小さく なる
4.本時の学習を振り返る
・全体で押さえるポイントを共有し、学習プリントにまとめさせる
・互いにプリントを見せあう時間をとってもよい
評価基準
1.自然現象への関心・意欲・態度
2.科学的な思考
B 2つの力を1つの力で表すことができることを気づく
3.実験・観察の技能・表現
B 平行四辺形を作図し、2つの力の合力を求められる
4.自然現象への知識理解
B 2つの力の合力は、平行四辺形の対気苦戦で表されることを理解できる
授業プリント例
生徒用
教師用(作図部分は手書きにより割愛)


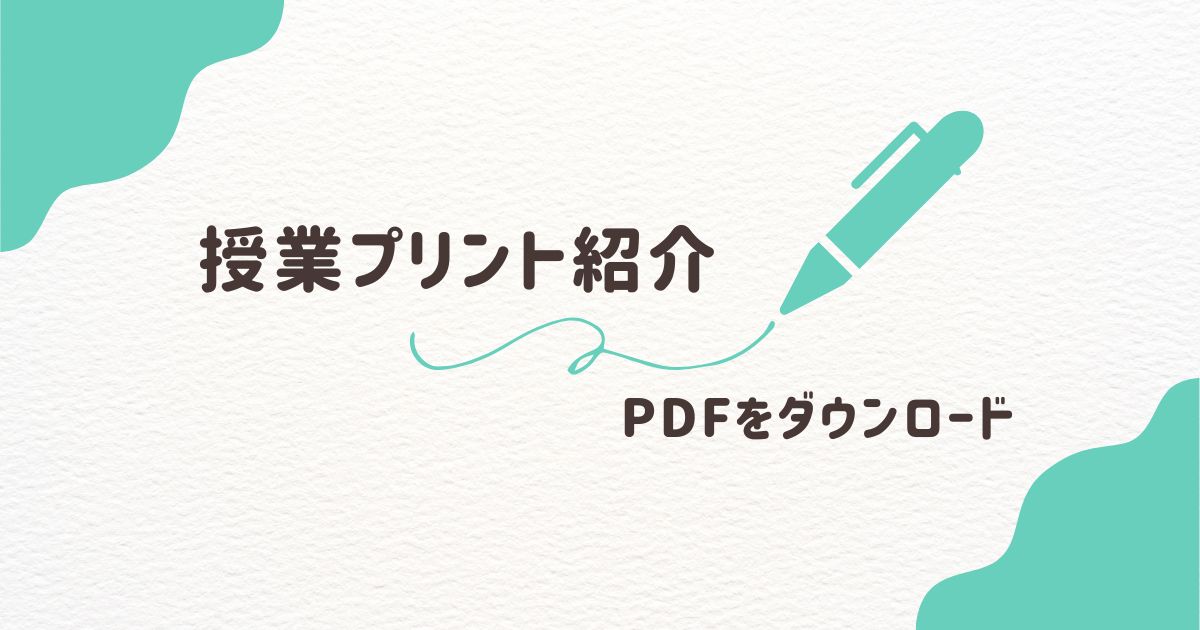
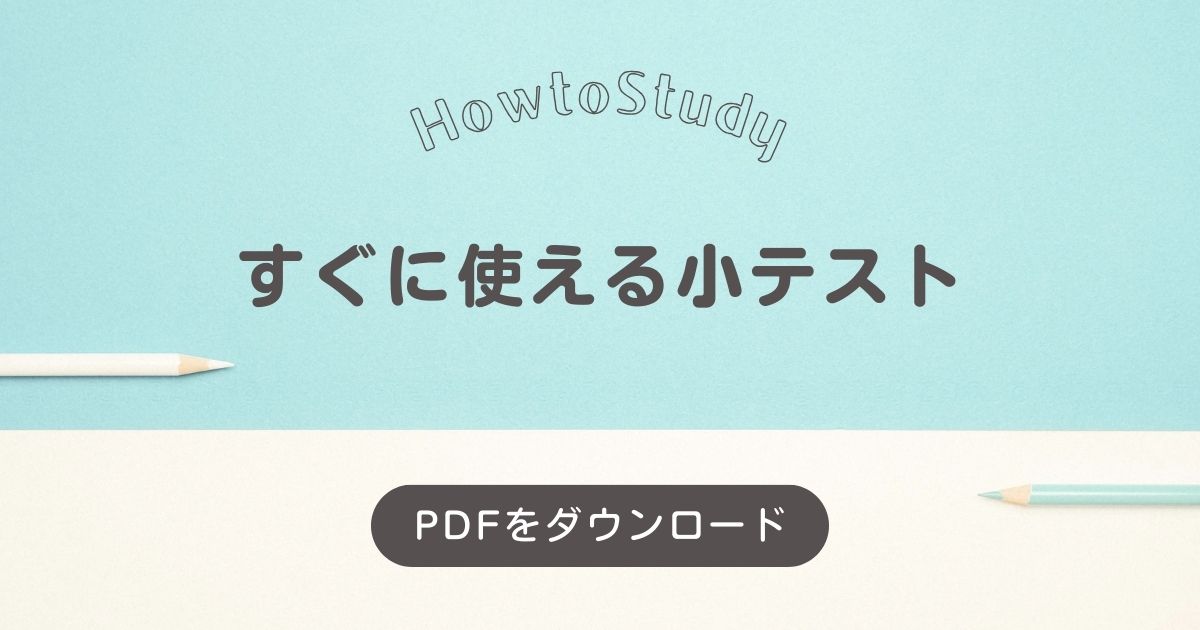
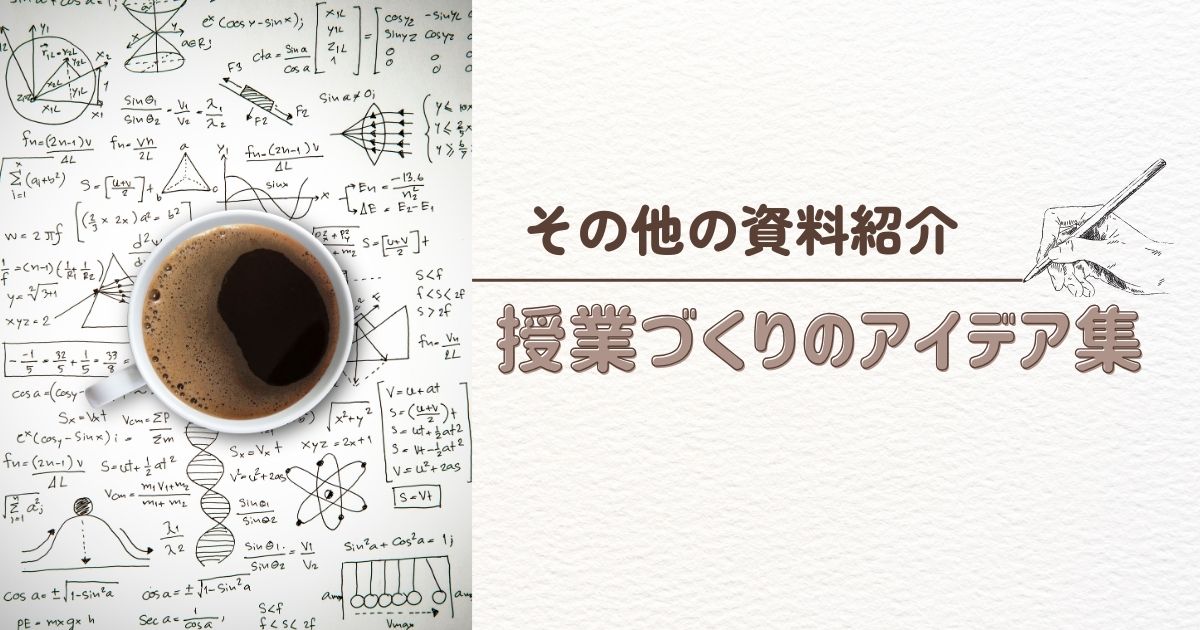
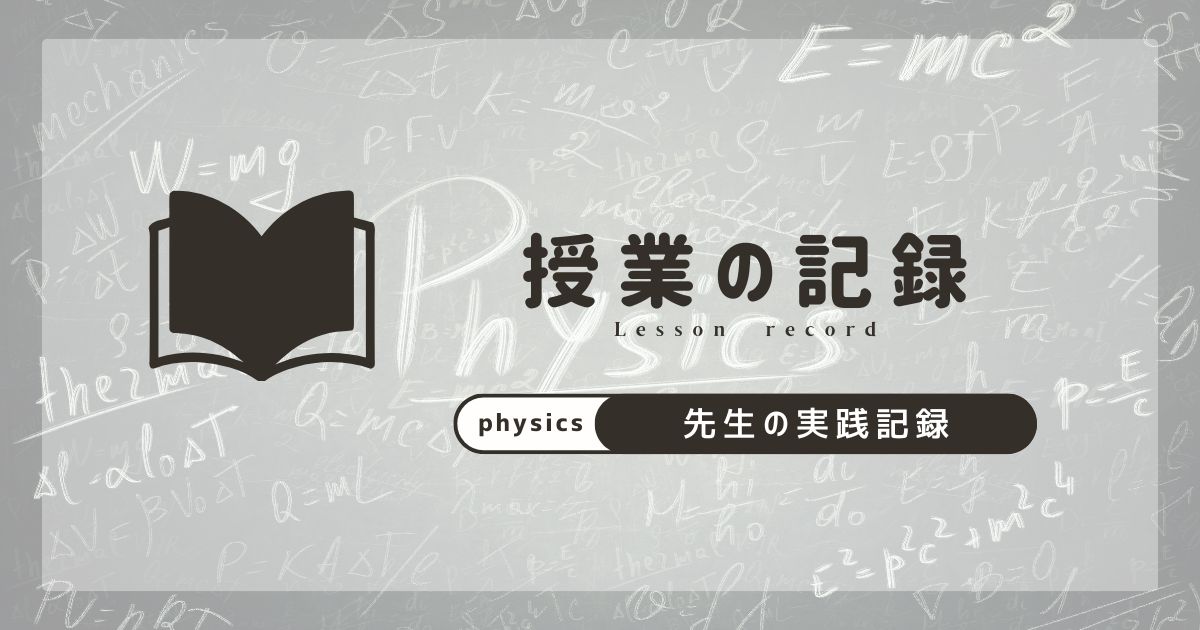



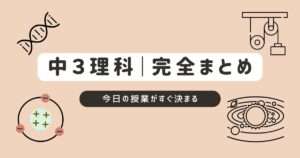
コメント